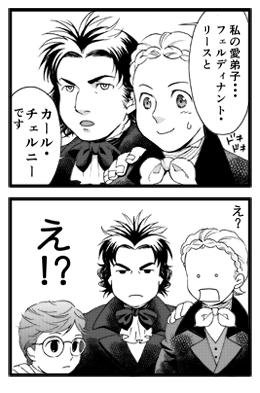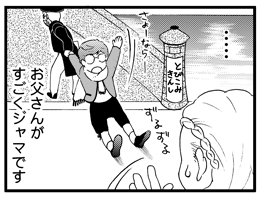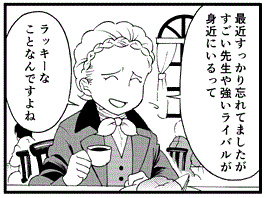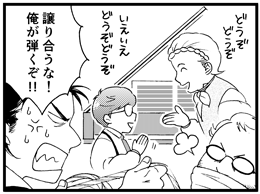「運命と呼ばないで」ネーム担当が、ガチ50%、妄想50%で語る
キャラクターズ・コラムVOL.1
~フェルディナント・リースとカール・チェルニー~
「グランド・ソナタ Op.160」とともに。

「運命と呼ばないで」Op.9より
●弟子たちは、不仲だった?
フェルディナント・リースとカール・チェルニー。ともに、ベートーヴェンの最もよく知られる愛弟子であり、また門下で過ごした時期もほぼ同じというふたりですが、彼ら弟子どうしがいかような仲にあったのか、ということについては、ほとんど正確な事実を知ることができません。
リースは、死の前年の1837年に、師ベートーヴェンと過ごした若き日の思い出を「覚書」として執筆しています。しかし、おそらく思いつくにまかせて様々な記憶の断片を書き連ねたのであろうその覚書には、驚いたことに、チェルニーの名前はただの一行も見当たりません。
一方のチェルニーは、その5年後の1842年に「自伝」、さらに10年後に「ベートーヴェンの逸話に関するメモ」を残しています。しかし、ベートーヴェンへの弟子入りの経緯を、映画のワンシーンのように鮮やかに描写しているその筆は、同門のもうひとりの弟子の話となると、まるで別人のように鈍ってしまうのです。
「リースと一緒に、私はよく2台のピアノでひきました。Op.47の「クロイツェル・ソナタ」もその中の1曲でしたが、この曲を私は2台のピアノ用に編曲しました。リースは達者にそして確実にひきましたが、冷たい感じのする演奏でした」
──「ベートーヴェンの逸話に関するメモ」より(「ベートーヴェン全作品の正しい奏法」全音楽譜出版社 P.20)

「運命と呼ばないで」Op.8より
このようになんとも情に乏しく、そっけない両者の態度をみると、親友や兄弟のように仲の良い弟子、といったイメージを抱くことはもちろん、互いに情熱をぶつけあう好敵手(ライバル)であった、という想像をすることさえ、ためらってしまいます。リースとチェルニーは7歳違いです。いくら同じ道を目指し、ときに同じ楽譜に相対し、ときに同じ呼吸とともに同じメロディを奏であう瞬間があったとはいえ、片や限りなく大人に近づきつつある、片やようやく幼年期を終えたばかりの少年が、相手のことを自らの似姿とみなし、甘噛みをしたり、牙を剥いたりするようなことは、そうそうありえないのかもしれません。
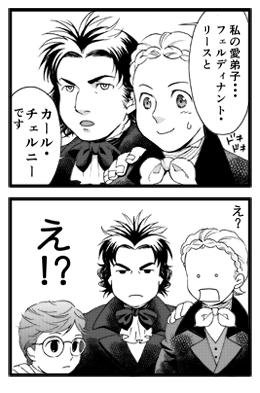
「運命と呼ばないで」Op.5より
●弟子たちは、おなじ記憶を共有している?
しかし、最も有名なベートーヴェン伝の著者であるアレクサンダー・ウィーロック・セイヤーは、リースとチェルニーの関係性について、必ずしもそのような見方をしていません。「歴史的な正確さ」を最大限に重視した研究者である彼は、しかし、このふたりの「愛弟子」について、意外なほど大胆な仮定を行っているのです。
「この才気ある二人の少年は、いつもいっしょのような形で、自分たちの有名な先生について、あきることを知らずに語りつづけるのが常であった。先生の風変りな点や奇行のいろいろ、作品をめぐるこまかな事実などの話は、それゆえ共通の所有物であった。つまりこのようにして、リースが知るようになったいくつかの事実は、いつのまにか記憶のなかで、自分自身の経験であったかのような気がしてきて、そういうものとして<<覚え書>>のなかに述べられているのである。」
──セイヤーの伝記より(「ベートーヴェンの生涯」音楽之友社 P.329)
セイヤーがここで仮定していることはふたつあります。1つ目は、この弟子ふたりが「あきることを知らずに語りつづける」ほどの親密な仲であったこと。2つ目は、その仲ゆえに、ふたりがいつしか胸に同じ記憶を共有していたということ。この説を信じるとするなら、彼らは、後年の思い出話から直接的に受ける印象ほどには、疎遠な間柄ではなかったはずです。実際のところ、ベートーヴェンの両脇にそれぞれ陣し、たえず才能を比較され、好奇の視線を浴びていたであろう彼らが、師の肩ごしの相手に対して、言葉にするのも億劫なほどの粗末な感情しか持ちあわせていなかったとは、そうそう思えないのです。
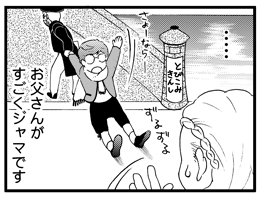
「運命と呼ばないで」Op.6より
●弟子たちは、何ゆえに口をとざした?
では、なぜ彼らの思い出話には、互いの痕跡がほとんど残されていないのでしょうか。その謎を解くためのヒントとして、リースの覚書に接する際に私が感じている、問題点について触れておきたいと思います。WEB4コマ漫画「運命と呼ばないで」のストーリーを作るときに、いつも苦労させられるところでもあるのですが、実は、リースの覚書には、正確な事実とはいえないような記述が散見されるのです。たとえばリースは、自分がボンからウィーンにやってきた年さえも間違えていますし、明らかに作曲年代の異なるベートーヴェンの作品を、自分が目撃したかのように書き記していたりします。これらの多くは、おそらく単純な記憶違いに基づくもので、当人に作為があったとは思えません。
しかし、もうひとつの問題はなかなか厄介です。これはもう完全に個人的な勘としかいえないのですが──リースの覚書には、故意に語るのを避けたのではないかと推測される事柄が──チェルニーの件を筆頭に、いくつか存在するのです。同じような勘を、私は、チェルニーが書いた自伝や逸話のメモに対しても働かせずにはいられません。彼ら弟子たちは、明らかに意識的に、互いのことに触れるのを恐れ、回避しているように思えてならないのです。「覚書」執筆当時のリースは53歳。「自伝」執筆当時のチェルニーは51歳。あの少年の日からは、すでに40年近くの歳月が過ぎていることになります。
厄介なことに、回想録というのは、過去の出来事そのものよりも、その時点から執筆の瞬間に至るまでの長い時間が生みだした歪みやもつれを、ときにより色濃く映しだしてしまうもののようです。もうあどけない「リース君」と「チェルニー君」ではない後年の彼らが、さまざまな人生の事情や思惑を背負ってしまった大人であり、また共にヨーロッパの楽壇の重鎮であった彼らが、互いの尊厳やキャリアにかかわる何らかの事情により、少年時代の思い出に鍵をかけてしまったとしても、懐かしい相手の輪郭を求めていまにも動こうとする筆を懸命に押しとどめ、書きかけたかもしれない懐古の言葉を暖炉の火にくべてしまったとしても、それを責めることは決してできません。
しかし、その代わり、そのぎこちない沈黙の周辺にただよう真実の気配というものは、たとえ何百年の時が過ぎたとしても、完全に隠蔽しきれるものではありません。そう信じなければ、もはやこの世に紙切れと墓石しか存在しない亡霊であるところの彼らを、生身の人間として理解しようと努めることは、きっとずっと難しいことになってしまうでしょう。片恋は、どれほど突拍子もない思い込みであったとしても、必ず何がしかの真実の一端を穿ちます。
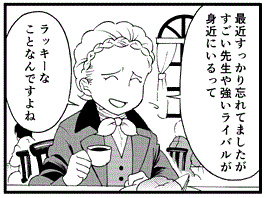
「運命と呼ばないで」Op.6より
●弟子たちは、音楽を交わしていた。
それでも、どうしたって証拠が乏しければ、その分だけ、真実の気配は危うさを帯び、消滅の危機に瀕します。リースとチェルニーは、少年時代、同じ門下の弟子同士として、ある程度の親密な仲にあったと思われる。しかし、どうやら何らかの事情により、人生の末に至るまで、その関係を維持することはできなかったらしい。どちらも所詮は想像の域を出ないこの2つの仮定を、より確信に近づけるための証拠は、何もないものでしょうか。
忘れてはならないことをここでひとつ繰り返しますが、彼らは音楽家です。日常や社会や政治や経済に隷属する以上に、音楽にひざまずくことを誓った人たちであり、そのために少なからず幼い頃から犠牲を払ってきた人たちです。できることなら、彼らが人生を賭けた他ならぬ「音楽」のなかに、その痕跡を見つけることはできないものでしょうか。──残念ながら、そのような願望を満たすための完璧な答えを見つけることは、いまのところできていません。ただ、偶然にもこのタイミングで録音がリリースされることになった、とある音楽作品が、そのひとつの手がかりになりうるかもしれない、と、私は考えています。フェルディナント・リースが、覚書を書くより6年前──1831年に手がけたその作品は、作曲目録には以下のように記載されています。
OPUS 160
Sonata for Pianoforte Duet
GRANDE SONATE / a quatre mains / pour le / PIANO /
Dediee / a Monsieur Charles Czerny / par son ami / FERD. RIES
4手のためのグランド・ソナタ、カール・チェルニー氏に捧ぐ、その友人フェルディナント・リースより、
作品160──。
──セシル・ヒルによるリース作品目録より(Ferdinand Ries. A Thematic Catalogue, Armidale 1977)
1831年。リースはフランクフルトに妻子と居を定め、音楽監督としての仕事やオラトリオの作曲に精を出していた頃。チェルニーはウィーンで、ピアノ教師と作曲に注力していた頃にあたります。リースがベートーヴェンのもとに弟子入りしてからちょうど30年後。そして、ベートーヴェンが亡くなってから4年後。少年時代から考えれば遠い最果てのような未来の地点に、彼らの”友 (ami)”としての情が行き着いていたこと。そして、最愛の師がすでに去ってしまったあとの世界で、少年時代の記憶を、師の記憶を、相手の記憶を共有したふたりが、何かを確かめ合うようにひとつの音楽作品を交わしていたこと。これは両者の関係を示すひとつの証拠であるといえるではないでしょうか。
それが純粋な友情なのか、ライバル心が長年をかけて変化を遂げた末の親愛なのか、共に一流になった男たちのエールの交わし合いなのか、師への追悼の意なのか、はたまた何がしかの孤独の吐露なのか、憐憫なのか感傷なのか涙なのかは、想像に任せるしかありません。残念ながら、この作品の献呈の際にリースがチェルニーに宛てたであろう手紙が見つかっていないため、彼の心情を正確に知ることも難しいように思われます。ただ、その3年前の1828年に、チェルニーからリースに対して先に2手のピアノ・ソナタ(Op.143)の献呈があり、それに対する「返礼」ではないかという推測はできるようです。
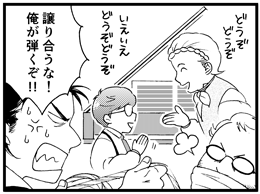
「運命と呼ばないで」Op.6より
2手(独奏)のピアノ・ソナタに対する、4手(連弾)のピアノ・ソナタの返礼。たとえ詳細は知れなくとも、リースがチェルニーに敢えて「2人のピアニストによって演奏される作品」を献呈したという事実から、彼の心情を推し量ることはできるのではないでしょうか。2人のピアニスト。それがリースとチェルニー自身でなかったとして、いったい誰と誰であるといえるだろうか?──と、私は思うのです。
「リースと一緒に、私はよく2台のピアノでひきました。」
──連弾と2台ピアノという違いはあるにせよ、チェルニーが重い口を開いてようやく書き残したあの言葉を、いまいちど思い出さずにはいられません。いまや遠い地に暮らし、まったく異なる音楽人生を生きている彼らには、直接再会してこれを弾くような暇もチャンスもありません。それにもかかわらず、リースが、この「グランド・ソナタ」と呼ぶにふさわしい、全3楽章、演奏時間にして30分以上に及ぶ大作を、若き日のライバルへ捧げたということ。そこに何か30年越しの特別な想いがあったということだけは、信じてみてもよいのではないでしょうか。たとえ、そのわずか6年後に、リースがチェルニーに関して一切口をとざしてしまったというもうひとつの現実が厳然と横たわっているにせよ。さらにそれから15年後に、チェルニーがリースの演奏について「冷たい」とそっけない感想を書き残しているにせよ。ベートーヴェンもリースもすでにこの世から消え、たった独りで膨大な記憶を背負ったチェルニーが、右腕にはもはや本当に弾くあてもない4手のピアノ・ソナタの楽譜を抱えて、左腕には自分の名前がひとつも無いリースの覚書を抱えて、冷たい、とつぶやいたとき、その脳裏には、確実に、第1楽章の冒頭のテーマが、意味深げに、そして力強く鳴っていたに違いないのですから。たったひとりのライバルが、自分に捧げたそのソナタの調べが。
(written by 「運命と呼ばないで」ネーム担当)
|